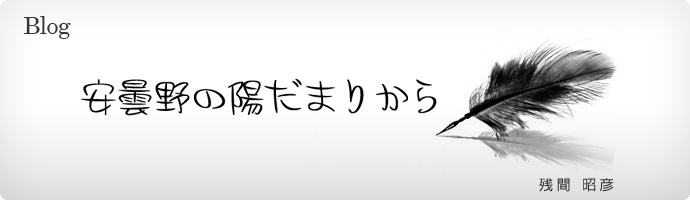
多くの姓が土地や職業・役職、あるいは動物などに由来している事はよく知られている。
対し、当家の「残間」という氏名(うじな)はその由緒の起こりが全く判らず、発祥のルーツについて長く疑問を持っていた。
そんな或る日、宮城県在住の芝修也さんのブログを見つけるに至った。
なんでも、母方の祖母の出自が残間家であり、幼いころより、かの一族の興亡の断片を聞かされていたらしい。
全国名字ランキング6128位という花々しからぬ名字について、以下に論考をまとめることとした。
至極パーソナルな事象に過ぎぬ物であるけれど、自画自賛の不遜を申せば、読み物としてそこそこ退屈はさせぬだろうと思うゆえ、耐えて笑読を乞う。
(※この文は、柴修也氏著「残間一族物語 ─ 政宗に山林六百町歩を献上した男 ─」に書かれた内容を元に要約・補足・再構成した小論である。)
芝 修 也
残 間 昭 彦
△ 現在の板谷御林の一部
伊達政宗が岩出山城へ入城し、奥州の覇者となったのが天正十九年(1591)の事であった。
しかし、その支配から遡ること数百年、ここ大谷邑《むら》の山を治めていた一豪族が在った歴史を知る人は少ない。
その者は政宗が岩出山に入るやいなや、先祖伝来の領地であった大山林を惜しげなく献上し、その地の御山守《おやまもり》の任へと下った。以後、明治維新に至るまでの凡そ二百八十年を、十二代にわたり一族は護りつづけ、その興亡の始終を膨大な文書として今に残した。
これは、後に「小・仙台藩郷土資料」とも称された、その編纂本を基に著わしたる山守人の物語である。
✻
△ 弘化4年築の残間家旧屋敷
その家は宮城県黒川郡大郷町東成田平田沢(通称板谷・旧大谷邑《むら》=大谷保)に十五代続く旧家であり、起源は、平家落人の一部が逃げ延びた先で集落をつくったと伝承されてきた。
しかし、現実的には、壇ノ浦で滅びた平家残党が千二百キロあまり離れた北の辺境まで落ち延び得たという説は考えにくい……。
そうした異論が声となりはじめた時期、 昭和五十八年、山村の或る家に所蔵されていた古文書が突如公開された。
それは、実に長持《ながもち》いっぱいの大冊の山であり、明治以降ほとんど開かずのまま奥座敷で埃をかぶっていたものであった。
驚愕のうち、大郷町教育委員会が解読・編纂に奔走し、それにより明かされた採録を一冊に綴じたものが「御山守残間家文書」である。
残間家は凡そ四百年来つづく旧家でありながら、藩の制度上では百姓並波となっていた。しかし、御林(藩直轄林)の御山守という特別な役目を代々伝えた名家であり、時に肝入(名主)や地肝入(村役人の筆頭)となった事もある。それ故、事実上は役人格の家柄と言え、それに相まって、伊達藩草創から明治維新に至るまで、全期三百年の記録が残った。
その膨大な文書を紐解く内訳はと言えば、村方、肝入文書、及び藩の法令・諸覚・留の類から、鉄砲、諸秘伝、教養などに関する内容まで、並みの山間郷士の家には有るべくもない、貴重な諸資料が集積されている。
加えて、日常の地方資料、生活、教養文化に関するものなど総数五百五十点も収録されており、これほど包括的なものは他にあまり類例を見ず、これにより、この家の祖先の成り立ちが推して知られるというものである。
✻
時代《とき》は武士政権確立総仕上げの頃、文治五年(1189)、源頼朝による奥州征伐(奥州合戦)が行われ、平泉を拠点として東北を支配していた藤原氏が滅亡した。
この時、頼朝と共に関東武士団が奥州にやって来て、黒川郷一帯を統治したのが菅原氏であった。
さらに、菅原氏譜代の或る家臣に板谷の山を含む大谷保の一部の地が賦与されるものとなり、その者が地名の板谷を姓《かばね》(称号)とした。
その後の板谷氏本流は、世にいう南北朝時代、足利尊氏討伐のため北畠顕家に伴い畿内《きない》へ侵攻し、界・滋賀などに領地を得ている。
対し、大谷保に止まった郎党《ろうとう》らは、「残留者を区別する」という意に因み残間と姓を名乗り、一帯を領する豪族となった。(〝間〟という文字には〝区切り〟〝隔て〟などの意味があり、また仏説によれば場所や時間も意味するらしい。したがい、「残った者たちの居所」という意にも解せる。)
以降、戦国騒乱の世に在った残間一族は、豪族の身でありながら武力に関わらず、山林に生業を営む分際として密かに存在しつづけた。
当時、大谷保一帯は葛西氏、黒川氏、留守氏、大崎氏などの勢力が入り混じる激動期にありながら、一族の領有地は誰の支配にも侵されず独立自足を保っていた。
言うなれば、山間の隠れ里のようなその地は、桃源郷の如き別天地であったのではと今に推考される。
✻
板谷の山に永い静穏の時は過ぎ、天正十八年(1590年)、豊臣秀吉による奥州仕置の争乱で、東北各大名の所領没収・所替えが強行された。
翌十九年(1591)伊達政宗が岩出山城に入城。
政宗の台頭により、残間一族は俄《にわ》かに近世の支配体制の突風を受け、戦国の俗世へと引きずり出される事となった。
戦さを避け領民の安寧を第一とするべく、若き当主、藤右衛門は自ら帰順の道を進んだ。
所領の多くである凡そ六百町歩の山林を政宗へ献上し、その功により、同地の御山守を任ぜられ、藤右衛門が残間家初代となった。
さらにその後、他の所領も召し上げとなり、その総額は優に七百町歩を超えたと伝わる。
それにしても、中世末期にこれだけの大山林を、一豪族風情が領有していたという事実のみでも一驚に値する。
然して、政宗から残間家への見返りは、租税の免除と年に僅かな報奨(金二切=五十両)を下されるに過ぎず、一族の暮らしは困窮を体《てい》した。
それにも拘らず、藤右衛門は、近隣農民らが自由に山へ入る事を許し、木材・山菜・漆などの伐採・採取や狩猟するを黙認していたという温情の人であった。

















コメントをつける