結文[小さな祈り]
夢であった。夢で良かった……、と胸をなでおろした。私は薄暗い講堂に大勢の若者たちと共に整列させられていた。遂に日本も“徴兵制”が施行され、迷彩 服を着た私たちは今まさに中東の戦線へおもむかんとしているのだ。どうにかここを逃げ出す手立てはないものかと思案しつつ、ふと窓の外を見ると、そこはまるで原爆直後の広島のように一望の荒野であった……。
3年前このレポートを書きはじめた頃から、私はこんな妙な夢ばかりを見るようになった。冗談ではない。本当にしょっちゅうこんな夢を見るのだ。ある時は戦場の豪にうずくまり、またある時は戒厳令下の街を彷徨い、そして遂には反戦活動の首謀者として官憲に捉えられ投獄されてしまうのだ。私はそれほどに戦争脅威へのストレスに苛まれているのだろうか……。自分でもよく分からないのだけれど、ともかくその悪夢が現実になることを想像するのが容易となった今、いったい本当の平和とは何だろうかとずっと考えつづけている。
本論にも触れてあるとおり、このレポートを書く切っ掛けとなったのは3年前の気ままな旅であった。
その年の正月休みのうちに概ねの骨子は書き上げたものの、突如勃発したイラク戦争から中東各地の紛争問題に対峙させられ、加筆と添削を繰り返し続けるはめに至ってしまった。けれど、一向に終焉を見ない紛争の泥沼化に苛まれつつ、いささか中途半端ながらも仮の結論とさせた小册を自費で製作するに踏み切り、広島・長崎をはじめとする全国数カ所の平和資料館等において販売をして頂く他、個人的な啓蒙と啓発に努めてきた。
そんなある日、仕事上の接点により以前から懇意にしていたS出版社の役員氏から電話があり、「君が贈ってくれた文を読み大変に感動した。ついては、その内容に興味を示している某出版社の社長と引き合わせたいので一度上京されたし……」との旨の連絡を頂戴した。雑誌編集が主であるS社の役員氏は、こうした内容の刊行を手掛け得る出版社数社へ私の文の一部をDMで送り、協力要請を働きかけていてくれたのだ。
この小論を世に出す術(すべ)を探らぬわけでもなかった私はその言葉に幾らかの期待を持ち、S社役員氏に伴われ某社へ赴いた。
80の齢(よわい)を越えておられると見受ける某社社長は、出版業界の重鎮などと称される割には存外と気さくに応ぜられ、まったくと言っていいほど尊大な威圧を感じさせない親しみを得る方であられた。
「文章の善し悪しは、添削、特に削で決まる。文章力学上強調するべき箇所以外は、思い切ってバッサリ削除しなければ文は読み易くならない……」などの多岐にわたる話しの最後に、自社の刊行物を2册私に預け、「あなたの文もこれくらいに仕上がれば当社で出版させて頂きますよ」と、前提を加えた。一応に押し頂き面 談の席を辞した私は、早速に車中でそのうちの1冊を開き目次に目を落とした。なかなかに興味をそそられる大説、と始めは思った。
その「平和と戦争の基礎知識」という題の論文の著者は「元大本営参謀」などという厳めしい肩書きを持っており、そうした立場と経験を基にした平和観及び戦争観を端的に書き下している。
始めのうちは、「安保とか防衛論と一口に言っても、やはり人それぞれに価値観念が違うのだな……」と、ふむふむと読み進んでいった。ところがそのうちに、どうも〝きな臭い〟なと思える発言が目立ってきた。「平和は望むだけで得られるものではない。平和を口にするのみで、それに値する努力をしない無責任な反戦主義者の机上論など、軟弱な土地の上に立派な建物を造ろうとするようなものだ」等々の意の言葉を巧みに用い、いかにももっともらしく言明し出したのだ。そして、それを理由に、立場のあいまいな自衛隊を軍隊に変えることによる軍事力の抑止を主とさせた平和論を提唱し、憲法の抑制により軍隊を持てない法への憤りと苛立ちを随所に記して憚らず、ついには「軍隊を持たない文明国は異様である」と断言させた。
しかし、軍隊を持つ国が多くなるほどに平和が近付くと誰が保障し、いったい誰が信じると言うのか。それこそアメリカの思う壷ではないか。
そうした近視眼的発想による論法こそ歪んだ机上論と断ぜざるをえず、失敬ながら、似非(えせ)平和主義者であると私は呼びたい。
未来永劫に戦争をしないと憲法に誓った日本であるならば、頑として非武装に徹し、他国への攻撃能力も意志も微塵なきことを公言するべきなのだ。無能な振りをした腰抜けの国など、テロも北も、襲うべき意気をなえさせるに違いない。何故なら、テロであれ北であれ、いかなる類いの〝先制攻撃〟も、その相手が脅威と成り得る者でなければ行わないからであり、要は山の中で熊に出会った時には死んだふりをするにかぎるという論法と同じだ。
しかるに、誰が何と言おうとも力を持たぬこと、それこそが最大の安保ではないだろうかと私は思う 。
さらに、著者が論ずる平和への方途観を知らされるにしたがい、私が取り分け違和感を覚えたところがある。それは、日本が過去に起こした戦争並びに事変の数々を延々と語る段におき、在りし日の日本軍の勇姿を賛美するがごとき文言や、著者自身の軍隊時代への郷愁めいたものを行間に覗かせるなど、結局は文明への寄与を口実にして戦争をあたかも必要悪であったかのように弁ずる件(くだり)である。私はその態度の裏に、末恐ろしき信念を伺い見る想いを得て閉口した。なぜなら、文明の発展を理由にして戦争を肯定する時、それは、経済発展のために地球環境や人身を犠牲にした、水俣病やサリドマイドなどの弊害をやむなき事と言う暴言に等しいと疑念するからだ。
詰まるところ、何ら結論的方策を見い出せない私の駄文に対し、氏のように明確な具体論の提唱を下す論が説得力を持ってしまうものだ。あの時、S社の役員氏にも言われた、「君の文は祈りに似ている」と。しかし、私はそれで良いと考えている。何となれば、ジョン・レノンの「イマジン」や「ラヴ」、ブラザース・フォアの「悲惨な戦争」などの歌を聴いて、祈るだけでは駄目だと、いったい誰が批判するであろうかと思うからだ。誰もが、あの曲を聴くだけで、あの歌を口ずさむだけで、充分に平和を愛する気持ちになれるはずだ。それが事実。それが平和であり、幸せというものではないだろうか。だから、平和は望むだけでいい、望み続ければ必ず成るのだ。平和を望み、地球を愛し、人類の未来を憂う人たちが沢山暮らしている星を〝絶対的平和の地〟と呼ぶのであり、そこには理屈っぽい正義も懐疑心を増長させる国防論も何もない。
つまりは、戦争の是非は旧約聖書に論じられるところの〝人類性悪説〟と〝人類性善説〟の議論に似ているいるような気がする。それは無史以来の疑問課題であり、キリスト自身でさえも「汝(なんじ)の敵を愛せ」と言った同じ舌で「目には目を、云々」と矛盾を言じたように、結論解決を下し難い難問なのであろう。がしかし、もしも人間は本来〝善〟なのであり、愛し合うべき生き物であるとしたならば、そこで即、戦い争う理由の総てが消えて無くなるのではないだろうか。青臭い夢物語りだと謗られようとも、少なくとも私はそう考えている。「空想的平和主義者!」と呼ばれ罵倒(ばとう)されるほどに、むしろそれ故に、私たちは決して言葉を失ってはいけないと鼓舞させられる思いを強める。
又、頂いたもう一冊「日本再生」なる書に至っては、とにかく〝憲法改正、憲法改正〟と繰り返し連呼し、果ては「戦争は権利である!」などと賢(さか)しらぶり、いさぎよく戦ってこそ文明国の本分であると、かつての特攻精神よろしく、イラク戦争の当事者二人(〝ブ〟と〝フ〟の両人)にある意味のエールを贈るごとき書き様であり、実にがっかりさせられた。
ともかくもそうしたわけで、某社との話しは見解の相違を招じ物別れとなったのだが、私はかえってそれで良かったと考えている。少なくともこの2書により、逆に、私自身の言動への確信と勇気を深めるに至ったという点におき有意を得たと思うからであり、自分の信じる概念を違えてまでも出版してもらう意味を理解しないからである。
ところで、実は前述の某社社長との面談の翌日夜半、私の父が急に危篤となり、さらにその翌日に急逝してしまった。本書文中にも登場させた、あの頑固親父がである。
父は昭和5年の生まれであるので、本来ならば戦争に行かなくても良いような年齢であった。しかし、当時の軍国主義教育に洗脳され、やむもたまらず中学2年の時に自ら志願して予科練に入ってしまった剛情者だ。両親や親戚 たちのいましめも聞かず「昔ならば元服して戦(いくさ)に行く歳だ!」とか何とか生意気なことを言々つつ、血気盛んと入隊してしまったのだと生前の父に聞かされていた(実戦には出なかったそうだ)。
そんな父が終(つい)の前に私へ残した遺言は、「この世は強者が威張り憚らず、弱者こそが悪である。人を利用しだましてでも強く生きろ」との一語に尽きていた。他人と闘い、自分と闘い、社会の理不尽と闘い、行政既得権の横暴と闘い、常に何物かと葛藤し続け生きてきた父らしい苦言であり、父もまた「優勝劣敗」という言葉の信仰にかられていた一人であったことを思い知った。
お人好しの私の性分を思いはかっての親心であるとしても、あまりに承服し難い言葉であった。最後の最後まで、エゴにも似た正義を振りかざす争いに終始し、どうしても勝つ事への執着を捨てられなかった父を私は哀れみ、しかし、それ故なおさらに愛おしむ。
四十九日を過ごした2か月後、当家菩提寺において父の納骨を済ませてきた。大地(つち)より産まれ育まれた父の身体を、そうして地球(つち)に還えしたのだ。ただ、それだけの事。ただそれだけの事ではあるけれど、失ったればこそ、これほどまでに父を深く愛し、好いていたことを思い知らされた。
かつて、傲岸(ごうがん)な父をうとんじ遠ざかった時期のある私が、遂に孝養はつくし得なかったまでも、せめて父を心から愛し逝かせる事ができた忠孝の微意を自らに認め、無理に納得することにした。
父に死なれた今、むしろ私は父を最も身近に感じる気がしている。こんなにも、常に父のことを想って過ごす日々はなかったからだ。こうして、父はいつまでも私の側に居てくれるのだろうか。「父よ、これから貴方は何も言わず、私の話しをただ黙って聞き続けるのか。人生観も平和観も全て私の生き方を否定し軟弱であると嫌っていた父よ、嗚呼 どうか、もう一度貴方の声を聞かせて欲しい……」
親の生が永遠でなきは必然、子より先に逝くも道理、「愛別離苦(あいべつりく)」が免れ難きも必定。しかし、はなはだ遺憾である。大いに遺憾である。
(中略)
肉親や大切な人が居なくなるという事実は、その死がいかなる理由によるとしても本当に辛いことであるのに何の違いもない。だからこそ、人の天寿全うを阻む戦争だけは決して許してはいけないのだと改めて考えさせられる。
生々流転…… 父が再び生まれ変わり、また青年になる時、「かつて地球上には国境というものが有り、人々は常に戦争を繰り返していた……」などと昔話に語られていることを望みたい。
最後となりここで思い出すのは、やはり彼の言葉である。
「我々が求めるべき真の平和とは、決してアメリカ人のための平和ではなく、全人類のための恒久的平和であらねばならず、アメリカあるいはどこかの国が、武力で強制するものであってはならない」ジョン・F・ケネディ
御笑読に深謝。
2007年3月20日
残間 昭彦
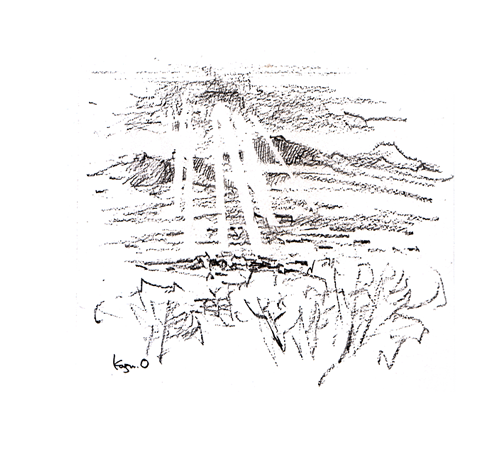

目次Contents
プロローグPrologue
第一章「戦争を見つめる」
- 原爆の爪痕 長崎原爆資料館にて
- 広島の黒い空
- 赤と黒だけの世界
- 悲惨な戦争
- 扉は必ず開かれる
- ケネディの遺言
- 共感共苦
- ソクラテスの憂鬱
- 一番になりたい症候群
- 天下の御意見番
- 大地の子
- 何ゆえの犠牲
- 鍬と胸飾と笛
第二章「平和を考える」
第三章「未来(あす)を望む」
- 平和への入口
- 音楽が伝えるもの
- 心のとまりぎ 安曇野平和芸術館の構想
- 泣けることの幸せ
- 無量の感謝
- 心の蘇生
- フラワーチルドレン
- あなたへ花を捧げたい
- 命こそ宝(ヌチドゥタカラ)
- 打ちそこねた終止符
- 炭坑のカナリア
- すれちがう言葉
- 確かな言葉
- 歓喜(よろこび)の歌




コメントをつける