非競争の論理
動物の世界には〝競争〟という概念が無い。だから、本当は〝ボス〟なんてものはいない。
「だけど猿の社会だって力の強いヤツがボスになるじゃないか……」という常識は、人間が勝手に思い込んでいる〝競争論理〟の枠にはめた理屈に外ならない。
強いヤツは群れの用心棒、ちょっと利口なヤツは渉外部長、いつも一番最初に動きだすのは先鋒(せんぽう)選手、真っ先に餌に手を出すのは単に意地汚いだけ……。そんなふうに、適材適所で個性と役割分担を発揮して互いに協力しあって生きている。
この事実は霊長類学者の間では意外と旧くから知られていた学説なのだそうだが、愚かな人間どもには〝ボス〟だ〝リーダー〟だ〝普通の猿〟だという社会構成で説明しなければ理解できないので、仕方なく〝ボス猿〟という名前で呼ぶに過ぎないのだ。
そうした、動物社会の常識に反し「力こそ正義だ!だから戦って権力を手にするんだ!」と、競争と攻撃を繰り返す下等人類がいる。自分の強さを他者に誇示するため、常に戦う相手がどこかにいなければ困るという変な人種のことだ。
そんな人間たちが「フロンティアスピリッツ」という耳触りの良い言葉を掲げ、17世紀のアメリカ大陸に続々と上陸した。そして彼らは、未開の先住民、ネイティブアメリカン(インディオ)たちから土地を奪い取り競って我が物にし、歯向うネイティブたちを攻撃的な野蛮種族だと言って殺りくした。そうした残虐非道の〝侵略者〟たちは、それを〝開拓時代〟と呼び国家樹立の起源とした。
開拓魂と言えば聞こえは良いが、その時から、私利私欲と自己顕示欲を満足させるために競争と戦争を繰り返すというアメリカの歴史が始まった。事実、争いを好まず先祖から受け継いだわずかな土地を耕すことに満足をしていた人たちは、イギリス、フランス、スペイン、イタリアなどの本来自分が居るべきところに止まった。そうした意味で、アメリカに新天地を求め移住してきた人たちの多くは、他人を倒してでも自分が勝ちたいと思う利己主義者だったのではないかと想像することがある。
それだから、アフリカから黒人を略奪してきては自分たちに迎合する奴隷までをもつくり、リンカーンの時代に至るまでそれを公然と奨励した。
領土争いの末の合衆国建国後も、暴力で他人の平穏を脅かす無法者アウトローがはびこり、正義という権威を振りかざした保安官が銃と力でそれを鎮圧した。そうした、数百年の歴史の要因が刻んだ彼らの遺伝子が争いを求め、いつしか外国との戦争に及ぶに至ったのではないか。
私に言わすれば、必要以上の動植物を侵さず自然と共生していたネイティブたちに打って代わり、あの異様なまでの飽食文化と飽きる事なき文明・経済の乱開発への欲望を見せつける彼等こそは、それこそ〝人喰い人種〟と揶揄(やゆ)したくなる思いだ。
(後半省略)
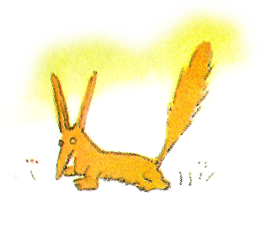

目次Contents
プロローグPrologue
第一章「戦争を見つめる」
- 原爆の爪痕 長崎原爆資料館にて
- 広島の黒い空
- 赤と黒だけの世界
- 悲惨な戦争
- 扉は必ず開かれる
- ケネディの遺言
- 共感共苦
- ソクラテスの憂鬱
- 一番になりたい症候群
- 天下の御意見番
- 大地の子
- 何ゆえの犠牲
- 鍬と胸飾と笛
第二章「平和を考える」
第三章「未来(あす)を望む」
- 平和への入口
- 音楽が伝えるもの
- 心のとまりぎ 安曇野平和芸術館の構想
- 泣けることの幸せ
- 無量の感謝
- 心の蘇生
- フラワーチルドレン
- あなたへ花を捧げたい
- 命こそ宝(ヌチドゥタカラ)
- 打ちそこねた終止符
- 炭坑のカナリア
- すれちがう言葉
- 確かな言葉
- 歓喜(よろこび)の歌




コメントをつける